焼きビーフンは、我が家のランチの人気メニューです。
でも、なんか旨みが足りないとか、炒めている(焼いている)うちにビーフンが切れてしまう!なんていうお悩みはありませんか?
そんなお悩み、2つのポイントをおさえれば、解決しちゃいます!
いつものビーフンを美味しくする、そんな2つのポイントをお伝えしますね。
目次
<レシピを無料でプレゼント中です!>
1 乾物の旨味を利用する

干しエビの旨味は、焼きビーフンには欠かせません
ビーフンの美味しさって、乾物の旨味からくるところが大きいと感じています。
基本は、干し椎茸の旨味と干しエビの旨味。
私はこれに、干し大根の旨味をさらに加えて作ることもあります。
干し椎茸の旨味
干し椎茸は、普段から水に浸けて冷蔵庫に保存しています。
戻し汁は、料理にダシとして少量加えます。
もちろん干し椎茸は、あれこれの料理に使います。
干し椎茸のグアニル酸という成分には、旨味を感じやすくする効果があります。
具体的には、私たちの舌にある、グルタミン酸という旨味の受容体が、旨味を捉えると離さないようにする働きをするというのです。
「旨味の相乗効果」と呼ばれるのは、こういう仕組みなのですね。
干しエビの旨味
干しエビは、ちょっとつぶして水に浸けて柔らかくしてから加えます。
10分くらい浸けておいて、その浸け汁ももちろん使います。
パウダーでも売られているので、それを加えるのも手軽です。
干しエビには、グルタミン酸とイノシン酸の二種類の旨味が含まれています。
干し大根の旨味
切り干し大根を加えるなら、15分ほど水で戻してから使います。
水溶性の成分や風味が含まれているので、この戻し汁も使います。
例えば、切り干し大根に多く含まれるカリウムは水溶性です。
2 ビーフンは茹でない方が美味しくなる理由

ビーフンは下茹でしないで!
ビーフンを作るとき、大概の方が、ビーフンを熱湯で茹でてから使っているのではないでしょうか?
袋にもそう書いてあることが多いし、私も以前はそうしてから炒めていました。
でも、炒めているうちにブチブチ切れてしまったり、食感がペニャペニャだったりで、あまり美味しく作ることができませんでした。
ある時、台湾のサイトを探していたら、
「ビーフンは下ゆでしないでそのまま加える方が、むしろ美味しい」
とあるのを発見して愕然としました。
旨みを出す乾物と旨みをもらう乾物
ビーフンも、乾物です!
乾物には、旨みを出す乾物と、旨みをもらう乾物があります。
旨みを出す乾物は、例えば先ほどあげた、干し大根や干し椎茸、干しエビのようなもの、あるいは昆布、鰹節などがあげられます。
お麩や高野豆腐は、反対に旨みをもらう乾物です。

車麩のフレンチトーストは、水で戻さずに、直接卵液に浸けて戻す方がぐっと美味しくなります
例えば車麩のフレンチトーストを作る時、水戻ししてから卵液につけるのと、直接卵液に浸けて戻すのとでは、後者の方がグッと美味しくなるのです。
水分が入ってしまっている分、卵液の成分が入りにくくなって水っぽくなってしまうからです。
そう考えれば、台湾のサイトの下ゆでしない方が良いというのも納得がいきます。
ビーフンは旨みをもらう乾物

キクラゲたっぷりビーフンは、食感も楽しい
ビーフンは、旨みを出す乾物ではなく、旨みをもらう乾物なのです。
肉や野菜などの具材を炒めてから鶏ガラスープと、乾物の戻し汁を多めに足し、沸騰したところにビーフンをそのまま入れて蓋をします。
たまに上下を返しながら、全体に液体が回るようにします。
しばらくすると美味しいダシを吸って、ビーフンが柔らかくなってきます。
この方法だとビーフンが切れてしまうこともなく、歯ごたえもいい感じで残ってとても美味しくなるのです。

たけのこの食感を生かしたビーフン
3 昨日はこんな風に作りました

ちょうど前日に、冷凍庫に溜まっていたエビの殻で出汁をとったところだったので、これをベースのスープにして、今回は干しエビは使いませんでした。
(エビ出汁は、ひたひたの湯に入れて15分ほど煮出して作ります)
旨みをかけ算することを考える
グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸が揃うと、美味しくなると覚えておきましょう。
- グルタミン酸は、多かれ少なかれほとんどの食材に含まれています。
- イノシン酸は、動物性の食材に多いと考えましょう。
- グアニル酸は、乾燥きのこ類に多いと捉えておきましょう。
この日に使った材料
- 生姜
- えび
- 玉ねぎ
- にんじん
- 干し椎茸
- 干し大根
- しめじ
- 満願寺唐辛子
- 乾物類の戻し汁
- エビの出汁
生姜を刻んで油とともに中華鍋に入れて弱火で香りを立てたところに、肉がなかったので、これも冷凍してあった小エビを加えます。
玉ねぎの薄切り、人参の千切り、冷蔵庫で一晩戻していた干し椎茸の薄切り、たまたま前日に戻して使い切れなかった聖護院大根の乾物の薄切り、しめじ、万願寺とうがらしの輪切りが具。
これらを中火で炒め合わせたところに、エビの出汁と干し椎茸や干し聖護院大根の戻し汁を多めに加えます。
(通常は、鶏ガラスープと乾物の戻し汁を使っています)
汁は多めでも、煮詰めればいいので分量は適当で大丈夫です。
基本の調味法
沸騰したら、紹興酒(なければ酒)、醤油、魚醤(ナムプラーなど)、オイスターソースを同分量で調味します。
そこにビーフンをそのまま投入。
上に書いたように、蓋をして蒸し焼きにしつつ、時々上下を返して全体に水分が吸収されるようにします。
5分ほどでしょうか。
水分がほぼなくなってきたら、風味づけにごま油を少々加えます。
麺が好みの硬さになったら出来上がりです。
火を止めてから、蓋をしたまま1分ほど蒸らすようにするとさらに美味しいとしている台湾サイトも見つけました。
味を馴染ませるということなのでしょうか。
ぜひ、試してみてくださいね。

今の時代だからこその乾物の活用法をお伝えする7回の無料メールレッスンを公開しています。
食品ロス削減、省エネ、もしもの時の備えにもなり、普段の料理が時短になる乾物を使う仲間になりませんか?


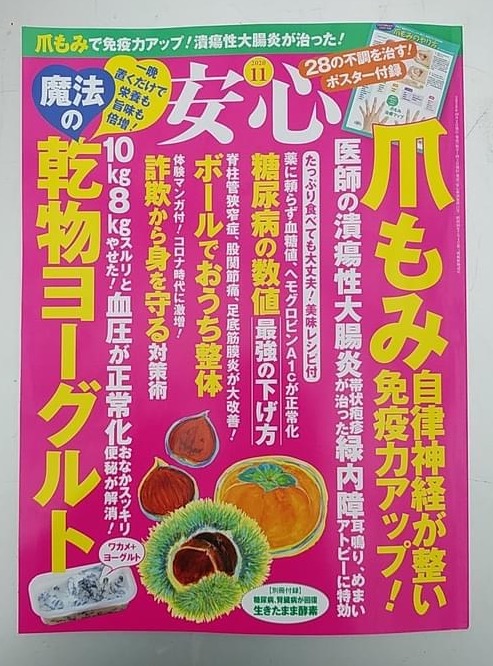











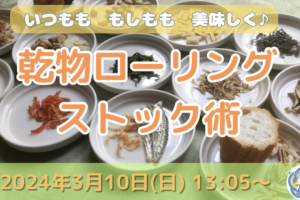



コメントを残す